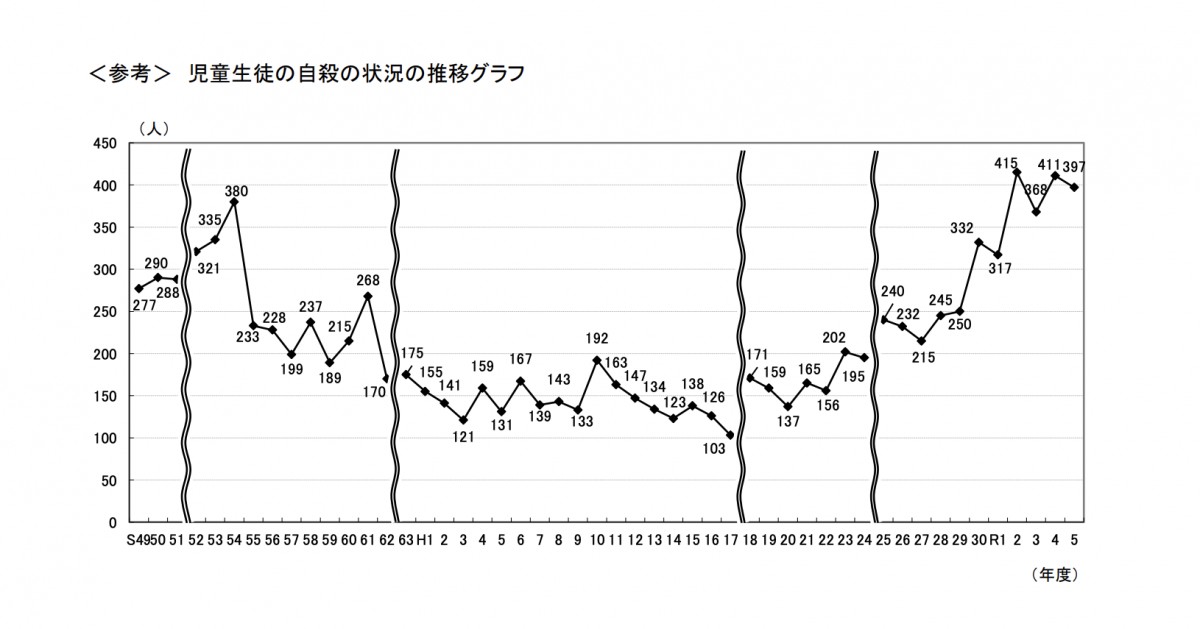いじめの事実や因果関係の認定に課題 「子どもいじめ防止学会」設立記念大会
弁護士、研究者、児童精神科医らで構成される「子どもいじめ防止学会」(理事長:野村武司弁護士)の設立記念大会が、東京経済大学(東京都国分寺市)で開催された。いじめ防止を専門とする学会はこれまでになく、2023年に設立された。大会では、2021年に北海道旭川市立中学校の2年生女子生徒(当時14歳)が、いじめを受けた後に自殺した事件をテーマにしたシンポジウムが行われた。第三者調査委員会の委員を務めた有識者が登壇し、いじめの事実認定、自殺との因果関係、責任の所在について議論しました。また、法律が定義する「いじめ」の概念とその問題点についても活発な議論が交わされました。

子どもいじめ防止学会で開かれたシンポジウム(撮影:渋井哲也)
いじめ防止対策推進法の定義と課題
2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」では、いじめを以下のように定義している。
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。
文部科学省はこれまで、いじめの定義から「自分よりも弱い者に対して一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言を削除した。そのため、法律上の「いじめ」と社会通念上の「いじめ」の範囲に乖離が生じている。教育現場では法律に基づく「いじめ」を前提に対応する必要があるが、この定義が十分に浸透しておらず、対応の遅れの一因となっている。
法律上の定義では、「行為」と「苦痛」がセットだ。「行為」は客観的だが、「苦痛」は主観だ。いじめと思われる行為があっても、被害者が「苦痛」を感じなければ、法律上はいじめと認定されない。故意や過失の有無にかかわらず、いじめが成立するのか、または「苦痛」の訴えがなければいじめとみなされないのか、といった議論がある。しかし、実際のいじめ対応では、「苦痛」の訴えがあれば、いじめの疑いとして扱われる。
一方、「苦痛」を口にしない場合でも、必ずしも「傷つき」がないわけではない。行為の「軽重」だけでいじめを判断できない難しさもある。旭川市の事件では、警察は「本人が被害を口にしていない」としていたが、女子生徒は動画配信者や地域の相談団体について相談していた。学校や教育委員会がどの時点でいじめを認定できたのかという課題が残る。そのためか、一部関係者はいまだに「いじめはなかった」と主張している。
いじめ定義の広さと限界
法律上の「いじめ」の定義を広範に解釈すれば、早期の認定ができるが、「失恋」なども含まれる懸念もある。シンポジウム以外の分科会でも、いじめの定義の広さに対する批判が研究者から出ていた。
旭川市の事件では、いじめがクラスや学校を超えた人間関係で発生していた点が問題を複雑にした。人間関係の範囲の実態は、学校外やオンラインゲームを通じたものになっていた。学校や教育委員会がネット上の人間関係をどこまで把握できるのかは、今後の課題だ。
さらに、旭川市の事件には性的いじめが含まれ、刑事事件の可能性があった。警察が刑事事件と判断した場合、学校や教育委員会の関与の範囲や対応の在り方が問題となる。わいせつ行為が「強いられた」ものかどうかを学校や教育委員会が判断するのは適切か、また刑事事件化した場合、学校の役割も明確ではない。いじめ防止対策推進法が、現実のいじめに対応しきれていない可能性が浮き彫りになった事件でもある。